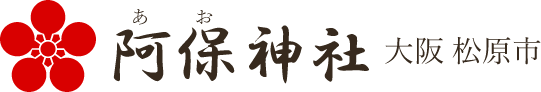いにしえの花天井

未来へ、つなぐ
元々拝殿に置かれていた四十八枚の花天井絵は、その描かれた年代や作者、また奉納された経緯など何もわからない状態でした。
しかも、長い年月の経過によってそれら絵の傷みもかなり激しくなっていました。
ただ、この地域の四季折々の樹木や草花を生き生きと描いた素晴らしいものでしたので、どうしても後世に残していきたいと考えました。
今回の修復後には『いにしえの花天井絵』として拝殿の保存ケースに大切に保管されることになりました。


経緯
令和四年四月花天井修復保存事業開始
令和五年八月花天井プロジェクトの構想立案
今和六年二月修復のため花天井絵の取り外し
今和六年十二月花天井プロジェクト完成記念奉納奉告祭ならびに除幕式典
修復された花天井画
-

うめ・紅梅
-

まつ
-

そてつ
-

おおたにわたり
-

くぬぎ
-

にしきぎ
-

すいせん
-

ぼたん
-

なんてん
-

つばき
-

はげいとう
-

りんどう
-

ぎぼうし
-

ざくろ
-

くさぼたん
-

きく
-

ごま
-

くり
-

へびいちご
-

おおいたび
-

じんちょうげ
-

とさかけいとう
-

はまなでしこ
-

ききょう
-

ぼんとくたで
-

のかんぞう
-

わた
-

せきちく
-

しゃくやく
-

あさがお
-

てっぽうゆり
-

ききょうらん
-

のうぜんかずら
-

のはなしょうぶ
-

びわ
-

むくげ
-

さくら
-

のじぎく
-

やまざくら
-

おおでまり
-

もくれん
-

くりんそう
-

たんぽぽ
-

げんげ
-

もみじ
-

やえつばき
-

うめ・白梅
-

たけ
未だ続く謎解き
令和四年夏頃、偶然にもある出会いがありました。
その先生は元・咲くやこの花館長でいらっしゃる久山敦先生で、植物の専門家です。
それまで、天井絵に関する名前の同定作業は遅々として進まず完全に行き詰まりを見せていましたが、先生との出会いでこの名前の同定作業が一気に進展し、完成に近づきました。
-

いわがらみ → おおでまり
いわがらみは、アジサイ科のツル性植物のため当初はこれではないかとしました。しかしいわがらみの花はガクアジサイのような咲き方であるのに対して、セイヨウアジサイの装飾花の雰囲気を持つ花として、似たものの中で、今回はおおでまりと変更することにしました。
おおでまりは、ヤブデマリの園芸品種で、4月頃にアジサイのような白い装飾花を多数咲かせ、庭木として有名です。
-

ぶっそうげ → とさかけいとう
これは難問中の一つでした。当初は真ん中の花の雰囲気がハイビスカスに似たものではないかとしてその中でブッソウゲ(仏桑花)としました。しかしやはり花のつけ根辺り、葉を観察すると、トサカケイトウにより近いとして、変更することになりました。
トサカケイトウは脳みそのような花が特長的で、漢字では『鶏冠鶏頭』と書き、その由来が見事に表現されています。
-

ふゆいちご → へびいちご
当初は野イチゴの一つとしてツル性小低木のふゆいちごではないかとしましたが、葉の感じからへびいちごと変更しました。
へびいちごは、人間は食べないことからへびいちごと名付けられましたが、実際には味がなくヘビも食べないらしいです。
-

めひしば → ぼんとくたで
当初は、いわゆる雑草と言われるイネ科のメヒシバではないかとしていましたが、花や葉のつけ根がタデ科のヤナギタデかボントクタデではないかとなり、結局はその姿からボントクタデに軍配が上がりました。
ボントクタデは、ヤナギタデのように辛味がないため愚か者との意味で名前がつきました。
このタデは『蓼食う虫も好き好き』と人の好みは多様であることを表現されてきたのです。
-

かわらなでしこ → はまなでしこ
これも難問中の一つでした。当初から花は明らかにナデシコ科の花なのに、葉がナデシコとしては違っているために、保留にしたいNo. 1でした。
その中で、久山敦先生からも、花芽のつき方や葉のイメージからはカワラナデシコよりはハマナデシコにより近いとの判断で、このように変更されることになりました。
ハマナデシコは、ナデシコ科ナデシコ属の一つで、この絵の中にあるセキチクにも近い花です。
またナデシコはサッカー日本女子代表の愛称にも用いられ、我が国にも深い縁のある花になります。
花天井絵の修復保存花天井絵の奉納
京都仏画研究所
代表絵師大里宗之様
絵師大里道子様
設計施工
所属先
設計施工上杉様